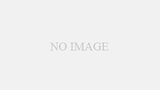子どもは、自身の力(自己教育力)によって自立、発達すると、正しい育ちの姿を見せるようになります(正常化)。しかし、大人の子どもへの誤った接し方などによって、子どもの自己教育力の発揮を妨げていると、子どもは「逸脱発達」してしまいます。
「逸脱発達」とは、「正常化への道筋を逸脱して発達している状態」のことです。モンテッソーリは、この逸脱発達を「強いタイプの逸脱」と「弱いタイプの逸脱」の二つに分類しています。
強いタイプの逸脱をしている子どもに現れる特徴
・わがまま ・攻撃
・乱暴 ・不従順
・発作的な怒り ・破壊的本能
・反抗的な行動 ・所有欲
・自分勝手 ・過食
・ねたみ(他の子が持っているものを取り上げて自分のものにしようとする)
・移り気
・手の動きを調整できないため、持っているものをよく落とす
・精神が無秩序なため、泣き叫んだりわめいたり、大きな物音を立てる
・友達の邪魔をしたりいじめたりする
・弱い子どもや動物に対して残酷なことをする
弱いタイプの逸脱をしている子どもに現れる特徴
・無気力 ・盗癖がある
・嘘をつく ・構ってもらいたがるが、すぐに退屈する
・拒食症 ・あらゆるものを怖がり、大人にすがりつく
・食欲不振 ・神経の異常
・過食 ・貧血(怖い夢や暗闇への恐れや不安定な睡眠が原因)
・泣くことによって何かを手に入れようとしたり、自分でやる代わりに他の人にやらせようとしたりする
大人が子どもに対して否定的な接し方をしていると、子どもは自身の力(自己教育力)によって自立、発達することができなくなってしまいます。
子どもに対する否定的な接し方とは、以下の3つです。
①過干渉…指示、命令、教え込みで子どもを管理する
いつも大人に管理され、命令されてその通りに動かなければならない環境にいると、子どもは自己教育力を発揮できなくなります。
②放任…「子どもには自分で育っていく力があるのであれば放っておこう」と考えて全く関わらない
確かに子どもには自己教育力がありますが、その力が発揮されるためには子どもの発達段階に見合う環境や教材、適切な指導が必要です。
大人が「環境を整えていない、整えたとしてもただ物を置いているだけで、そのやり方を子どもに伝えていない」のに子どもをほったらかしにしていると、子どもはその環境とどのように関わったら良いかがわからず自己教育力を発揮できないばかりか、「やりたい放題」になり、我慢のできない人間になってしまいます。
③発達を阻害…子どもの育ちを阻害する物を使用する
例)テレビ(知性、言語、感情の発達が阻害される)
おしゃぶり(言語の発達が遅れる)
柵(見えるものがないと、視覚の発達が促されない)