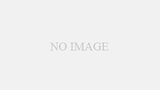「話しことばの敏感期」に対応する人的環境
①子どもに正しい発音で美しい会話をたくさん聞かせる。
※方言はその土地の文化であるため使ってよい。
②子どもの視線に合わせ、口元を見せてゆっくりはっきりした口調で話す。
③繰り返し同じことばを聞かせる。
④実物や動作にことばを添えて、生きたことばになるようにする。
⑤ゆったりとした時間をつくり、子どもが落ち着いて話せるようにする。
⑥子どもの発語を促すような聞き方、話し方を心掛ける。
「話しことばの敏感期」に対応する物的環境
・「物と名前」(1歳くらいから)

☆目的☆
実物からイメージを形成する
語彙を増やし、豊かにする
子どもの日常生活の中にある、果物や野菜などの実物が、果物なら果物だけ、野菜なら野菜だけというように仲間分けされてかごに3~6個くらい用意されているものです。それらを1つずつ手に取り、手に取った物の名称を言っていきます。具体の最たるものである「実物」の果物や野菜であるため、実際に触れたり匂いを嗅いだりしながらことばを理解していくことができます。
☆手順☆
①大人が実物を手に取り、「これは、~です」と名称を言う。その際、子どもと一緒に触ったり匂いを嗅いだりする。
②残りの物も同様に行う。
③子どもに、「~はどれかな?」などと言い、答えてもらう。
・「絵本」(1歳くらいから)

☆目的☆
語彙を豊かにする
絵本の楽しさを知る
想像力、理解力を養う
☆手順☆
①題名を読む。
②ページを丁寧にゆっくりめくり、子どもに絵を見せて、ゆっくりはっきりと読み始める。
③読み終わったら「おしまい」と言う。
☆どのような絵本が良いか☆
・日常生活や遊びの中にあり、子どもにとってなじみのある事柄をテーマにしている
・事物が豊かに表現されている
・絵だけで楽しめる
・ことばのリズムが心地良い
・繰り返しがある
・ストーリー性がある
・「物と絵カード」(「物と名前」を終えた子どもが対象)
☆目的☆
実物またはレプリカからイメージを形成する
語彙を増やし、豊かにする
子どもの日常生活の中にある、果物や野菜などの実物、もしくは動物や乗り物などのレプリカと、それらと同寸同色の絵カードを対応させます。実物やレプリカという「具体物」だけではなく、絵カードという「半抽象」のものを理解できるようになることも、この教具の大きな特徴です。初めのうちは実物やレプリカと同寸同色の絵カードを使用しますが、次第に同寸同色ではなく「類似する」絵カードを使用するようにしていき、さらに抽象度を増しながら、全く同一でなくても本質を捉えることができるように促していきます。
☆手順☆
①絵カードを取り出し、「これは、~の絵です」と名称を言ってから、順次並べる。
②絵カードと同じ実物、またはレプリカを取り出し、カードの絵の上にぴったりのせる。
③同じであることを確認した後、再度名称を言う。
④同様にして全ての絵カードを対応させる。
・「命名のカード」(「物と絵カード」を終えた子どもが対象)
☆目的☆
語彙を増やし、豊かにする
子どもの日常生活の中にある、果物や野菜、乗り物、遊具などのテーマによって分類された絵カード、もしくは写真を、1枚ずつ手に取り、そのカードの絵の名称を言っていくものです。今までの教具と異なり、「具体」である「物」がなく、「半抽象」の絵や写真だけでことばを伝えていく教具です。
☆手順☆
①絵カードを取り出し、「これは、~の絵です」と名称を言ってから、順次並べる。
②子どもに、「~の絵はどれかな~?」などと言い、答えてもらう。
・「ひみつ袋」(2歳くらいから)

☆目的☆
語彙を豊かにする
実体認識感覚(触覚と筋肉感覚)を養う
※筋肉感覚とは、筋肉の収縮や緊張の状況を知覚する感覚のことです。
子どもが日常生活の中で使っている物やよく知っている物のミニチュアなどで、危険性がない物が、5個くらい入っている袋です。乗り物が大好きな子どもには乗り物のミニチュアを用意するなど、子どもの興味関心に合った物を袋に入れると良いでしょう。
☆手順☆
①袋の中の物を、見ないで名称を言ってから出すことを子どもに伝える。
②袋に手を入れて物に触り、その物の名称を言ってから一つずつ出して、置く。